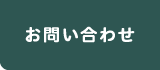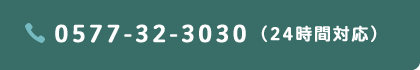葬儀の流れ
- HOME |
- 葬儀の流れ
基本的な流れ
きめ細やかな対応と運営でスムーズにサポート
仏式葬儀の一般的な流れをご紹介いたします。
ご心配な方はぜひ一度ご相談ください。

ご臨終~移動
-
- STEP1身内が危篤を告げられたら・臨終を迎えたら
- STEP2家族近親者への連絡
- STEP3葬儀社への手配
- STEP4ご遺体の移動

安置~湯かんと納棺
-
- STEP1ご遺体の安置(自宅に運んだ場合)
- STEP2葬儀プランの打合せ
- STEP3湯かん・納棺
ご臨終~移動
- STEP1身内が危篤を告げられたら・臨終を迎えたら
-
身内の誰かが危篤・臨終になった場合、やらなければならないことがたくさんあります。しかし、喪主の経験がない方にとっては「知らないことばかり」ではないでしょうか。知っておくことで、いざというときも慌てず対応できるでしょう。
危篤 医師が容体などを見て判断する「命の危険が迫っている状態」のことです。危篤と判断されてから数時間で亡くなってしまうこともあれば、数日間にわたってその状態が続くこともありますし、回復するケースもあります。 臨終 死に直面することや、亡くなることを意味します。 - 1病院で亡くなった場合
-
- 医師によって死亡確認が行われます。確認が済むと、死亡を証明する書類「死亡診断書」が作成されます。
- 看護師が故人の体の処置(エンゼルケア)を行ってくれます。
お湯やアルコールで体を拭き、耳や鼻に脱脂綿を詰め、着替えや死化粧を施してくれます。
- 病院でレンタルした衣類は返さなくてはいけません。あらかじめ浴衣などを用意して持っていくと良いです。院内の売店で購入することもできます。
いわゆる「死装束」と呼ばれるような真っ白なものである必要はありません。出血などで汚れることもありますし、納棺の際に着替えさせるまでの一時的なものです。
故人の体は硬直していたり、傷や水疱が出来ていることがあるため、出来るだけ大きく動かさない方が良いです。したがって、前を開ききってしまえて、首や腰の部分が狭くなっていない「浴衣」が適当です。
- 2自宅で亡くなった場合
-
- 自宅での看取りや療養を行っていた場合は、真っ先にかかりつけ医に連絡します。
かかりつけ医から24時間以内に診察を受けていて、持病などによって亡くなった場合は、臨終の立ち会いがなくても死亡診断書を作成してもらえるのが普通です。
24時間以内に診察を受けていなくても、かかりつけ医に持病により亡くなったことを確認してもらえれば、死亡診断書を作成してもらえます。 - 予期せず自宅で亡くなり、死亡の判断が難しい場合や、かかりつけ医がすぐに自宅へこれそうにない場合などは、救急車を呼びます。
蘇生する可能性があれば、病院へ搬送してもらうことが可能です。明らかに死亡していることが分かれば、救急隊員は警察を呼んで帰ってしまいます。 - 明らかに亡くなっていると判断できる場合や、不審な点があるなど事件性が疑われる場合は、警察に連絡します。
この場合、万が一の事件性の有無を確認するため、医師の死亡確認が行われるまでは遺体を動かしてはいけません。
入浴中に亡くなられた方を浴槽から出してしまったり、服を着せてしまったりすると、死因の特定が難しくなったり、取り調べを受けることになったり近所への聞き取りが行われるなど、その後の手続きが複雑になってしまうので注意が必要です。
ただし、亡くなっていることが確実ではなく、状況に応じて心肺蘇生などを行う必要がある場合は平らな場所に移動させても問題ありません。
- 自宅での看取りや療養を行っていた場合は、真っ先にかかりつけ医に連絡します。
- 3施設で亡くなった場合
-
施設で亡くなった場合、死亡確認を行うまでに時間がかかることがあります。
医師が常駐していない施設の場合、提携医療機関の医師などが死亡確認を行うため、すぐに駆けつけられない場合があるからです。
- STEP2家族近親者への連絡
-
医師から危篤と告げられたら、家族や親戚に連絡をして、病室などに集まります。連絡をする時は、落ち着いて、分かりやすく伝えましょう。
連絡する時間帯などは、それほど気にしなくても構いません。最期に立ちあえるよう、速やかな対応と連絡が大切です。家族・近親者への連絡
対象は一般的に「3親等以内の親戚」と言われていますが、日頃の付き合いも考えて連絡します。
家族や親戚に限らず、日ごろの交友関係を踏まえて、親しい人がいる場合は連絡することもあります。
基準は、「最期に立ち会ってもらいたい人」です。職場や学校への連絡
自分が休むことで仕事に支障が出ることもあるでしょう。職場の上司や同僚には、早い段階で連絡しておきます。
深夜や早朝などは避け、時間をおいてから改めて電話します。基本的に朝は7時以降であれば、差し支えありません。
危篤状態が何日か続く場合にも、こまめに状況を伝えます。危篤の場合は「有給休暇」を使って休みます。家族が亡くなってから休む場合は「忌引休暇」を使って休みます。
日数などは会社によって異なるので、事前に確認しておきましょう。故人との続柄によって取得できる日数が異なります。配偶者や親の場合は長め、その他の親族の場合は短いのが一般的です。連絡を受けたら
知らせを受けた場合は、落ち着いて行動することが大切です。病院などに向かう途中で、事故を起こさないように注意しましょう。
また、心の準備をしておく必要があります。
面会に行く場合、服装にこだわる必要はありませんし、お見舞いを持って行く必要もありません。
- STEP3葬儀社への手配
-
いつ臨終を迎えるか分かりません。
慌ててしまい冷静な判断ができなくなるかも知れません。いざという時のため、依頼する葬儀社を決めておくと良いです。
何をしたら良いか、葬儀社が整理して教えてくれるので、いくらか不安が軽減されるはずです。
- STEP4ご遺体の移動
-
病院や施設で亡くなった場合
病院や施設で亡くなった場合、そこからご遺体を安置できる場所(自宅や三礼の安置室)に移動させなくてはいけません。
故人の体の処置(エンゼルケア)が終わる頃には、死亡診断書の作成が終わります。その時間にあわせて、三礼が搬送車両で迎えに行くのです。移動先を決めて、葬儀社に搬送依頼をする
看護師や施設の関係者に確認して、「ご遺体を運び出せる時間」と、「ご遺体の移動先」を先回り三礼にお知らせください。
- 注 意電話までに決めておくこと、確認しておくこと
-
お電話でご相談する際、弊社から以下のことをお尋ねさせていただきます。
- 1どこにご遺体を運んで安置したいですか?
-
親戚が集まったり、お寺さんが来たり、近所の方が弔問に来たりします。
家の中が片付いていない・駐車スペースが足りない・家族葬をしたいから近所に知られたくないなど、ご事情にあわせて、直接「三礼の安置室」に運んで安置することが可能です。ご自宅へ運ぶ場合
仏間に安置するのが一般的です。
しかし、「仏間は、急な階段をあがった2階にある」とか「仏間が物置代わりになってしまっている」など、仏間の使用が難しいなら、「仏間以外の部屋」でも構いません。
- 2何時にお迎えに行ったら良いですか?
- 死亡診断書を受け取らないとご遺体を運び出せません。三礼も、お宅を地図で調べたり必要な道具を用意する時間があるので、最低1時間は必要です。
- 3ご自宅で安置をするための準備は出来ていますか?人手はありますか?
-
ご自宅に到着したら、ご遺体を安置する部屋に運びます。速やかに安置ができるよう、お身内で手分けして、先回り準備をしてください。
- 安置する部屋に布団(掛布団と敷布団どちらも)を用意しておいてください。
- 納棺が済むと、布団は必要無くなります。三礼が無料で引き取り処分させていただくことも可能です。ご相談ください。
- 安置には、特別な布団を使うわけではありません。シーツやカバーが無くても構いません。三礼が用意する棺用の布団は、安置のシーツやカバーの代わりに使えます。
- 布団が無い場合は、早めにお知らせください。有料の安置布団を用意して参ります。
- 自宅に到着したら、安置場所に運ぶための人手が必要です。足腰に不安をお持ちでない方にお手伝いいただきます。
- 夜間は、「2階の仏間に上げる」などの人手を要するご要望にお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 玄関のカギを開けておいてください。
- ご遺体を搬送してきた車が、ご遺体を降ろし終えるまでの間、停車いたします。
- 葬儀日程の打合せなどを行う2~3時間、スタッフの車を1台停めさせていただきます。
- 安置する部屋に布団(掛布団と敷布団どちらも)を用意しておいてください。
- 4手次寺(てつぎでら)・菩提寺(ぼだいじ)はどこですか?
-
葬儀や年忌法要を行ってくれる、普段からお付き合いしているお寺はどこかお聞きします。
安置が済んで程なくしたら、そのお寺さんに来てもらって読経してもらい、お寺さんを交えて葬儀日時・火葬時間などの打合せを行います。また、お寺によって、三礼が準備しなくてはいけない道具が違うので、先に知っておきたいのです。
- 5三礼互助会の会員ですか?
-
三礼互助会の契約をなさっていても、それを離れて暮らすご家族には伝えていらっしゃらないというお客様も時おりいらっしゃいます。
ぜひ、情報を共有しておいてください。会員になっておくと、葬儀費用を抑えることができます。
互助会のご契約についてはしっかりデータ管理をしておりますが、念のためお尋ねします。
電話例

以下は、電話対応例です。
ご参考になさってください。- A病院で亡くなられ 病院にいる息子(A)さんからの電話
-
◎◎町の□□です。
先ほど病院で 父 が亡くなりましたので、葬儀をお願いしたいです。それはお気の毒なさいました。では、順にお聞きします。
亡くなられた方のお名前を教えてください。□□太郎です。
お電話くださいましたお宅様 お名前と 太郎様とのご関係を教えてください。
私は 同居している息子のAです。
今いらっしゃるのは、病院ですか?病棟・病室を教えてください。
△△病院 2病棟 3階の311号室です。
看護師さんによるご処置は、始まりましたか?
はい。10時20分頃終わるそうです。
まもなく死亡診断書も受け取れるようです。それでは10時30分にお迎えにあがります。
どこへお連れしたらよろしいでしょうか?自宅に連れ帰りたいです。
わかりました。
ご自宅のご住所・お電話番号を教えてください。◎◎町 ○丁目 ○番地。0577-○○-○○○○です。
ご自宅のご安置するお部屋には、掛布団・敷布団が必要です。
どなたか、ご自宅でその準備ができますか?私の弟が、今、自宅で準備しています。
最後に、2つ教えてください。
三礼互助会の会員さんですか?はい、太郎の名前で契約しています。
□□家様のお寺はどちらですか?
○○寺さんです。
わかりました。
では、10時30分に△△病院にお迎えにうかがい、◎◎町のご自宅にお連れします。わかりました。よろしくお願いします。
- B介護施設で亡くなられ 自宅にいる娘(B)さんからの電話
-
◎◎町の□□です。
先ほど、入所していた施設で 母 が亡くなりましたので、葬儀をお願いしたいです。それはお気の毒なさいました。では、順にお聞きします。
亡くなられた方のお名前を教えてください。□□花子です。
お電話くださいましたお宅様 お名前と 花子様とのご関係を教えてください。
私は 二女のBです。
今いらっしゃるのは、どこの施設ですか?
◇◇町の◉◉ホームです。
看護師さんによるご処置は、始まりましたか?
はい。10時20分頃終わるそうです。
まもなく死亡診断書も受け取れるようです。それでは10時30分にお迎えにあがります。
どこへお連れしたらよろしいでしょうか?家は、何年も留守で散らかっているので、どうしようか困っています。
わかりました。
それでしたら、三礼のご安置の部屋をお使いいただくことができます。付き添って泊まれますか?
畳部屋が付いていますので、そこでお休みいただけます。
分かりました。ではその部屋に連れて行って欲しいです。
最後に、2つ教えてください。
三礼互助会の会員さんですか?はい、花子の夫の太郎の名前で契約しています。
互助会をお調べする時に必要なので、教えてください。
ご自宅の住所・電話を教えてください。◎◎町○番地。
0577- ○○ - ○○○○です。□□家様のお寺はどちらですか?
○○寺さんです。
わかりました。
では、10時30分に◉◉ホームにお迎えにうかがい、三礼の安置室にお連れします。わかりました。よろしくお願いします。
- C自宅で亡くなられ 自宅にいるお孫(C)さんからの電話
-
◎◎町の□□です。
先ほど、在宅で介護していた 祖父 が亡くなりましたので、葬儀をお願いしたいです。それはお気の毒なさいました。では、順にお聞きします。
亡くなられた方のお名前を教えてください。□□一郎です。
お電話くださいましたお宅様 お名前と 一郎様とのご関係を教えてください。
私は 孫のCです。
お伺いするご自宅の住所・電話を教えてください。
◎◎町○番地。
0577- ○○ - ○○○○です。看護師さんによるご処置は、始まりましたか?
はい。先ほど終わられて、帰られました。
死亡診断書は受け取られましたか?
先生が診察に戻られたので、夕方、届けて下さるそうです。
それでは、ただ今9時20分ですので、準備をして、1時間程後の10時30分にお邪魔します。
分かりました。お待ちしています。
最後に、2つ教えてください。
三礼互助会の会員さんですか?はい、昨年、私の名前で契約しました。
私の住所は、⦿⦿町〇〇番地です。□□家様のお寺はどちらですか?
○○寺さんです。
わかりました。
では、10時30分頃、ご自宅にお邪魔します。わかりました。よろしくお願いします。
安置~湯かんと納棺
- STEP1ご遺体の安置(自宅に運んだ場合)
-
布団に寝かせる。
運ぶ際に、ご家族様1~2人にお手伝いいただきます。
「故人を北枕で寝かせる」という風習があります。お釈迦様が亡くなられたときの向きにならったものですが、間取りの都合や動線、仏壇の位置を考慮して、三礼が無理のない安置をご提案します。ご遺体を冷却する。
ご遺体の状態の変化を遅らせるためには、室温を低くし、ドライアイスで冷却することがとても重要です。
夏場は冷房を効かせて18~20℃ぐらいに保ち、冬場は暖房を切るなどして室温を低くします。
ドライアイスはどんどん気化して小さくなってしまいます。気化を早めてしまうので、扇風機で風をあてることは逆効果だと言われています。
薄くて軽い通気性の良い布団より、昔ながらの綿の重い掛布団を使うことで、密閉された状態になるため、ドライアイスの効果がある程度が長持ちするようです。故人様の身支度。
主に、仏教の葬儀を行うための準備をします。お分かりにならないこと、不安なことがありましたらご相談ください。その場でスタッフがアドバイスやお手伝いいたします。
生前に法名・戒名を授かっている場合、それが記されたものがあるはずです。仏壇の引き出しが一般的な保管場所です。枕元に出しておきましょう。枕飾りを設置する。

自宅での安置が済んだら、ご遺体の枕元に枕飾りと呼ばれる小さな祭壇を置きます。お寺さんに来てもらって読経してもらう仏教の儀式の準備です。
枕経は、元々は臨終を迎える方の枕元で行う儀式でした。病院で臨終を迎える方が多くなったため、今ではご遺体が安置されてから行います。
宗派によっては、枕飾りの上に「お水」や「一膳めし」を置く場合もあります。三礼がアドバイスいたします。
仏壇の準備をする。
仏壇がある場合は、打ち敷き(うちしき)を白色に変えます。持っていない場合は、可能ならば購入しておきましょう。
花を供えて、ロウソクを灯します。香炉が汚れていたら、掃除をしておきます。
地域によっては、仏壇の扉を閉めてしまうそうですが、飛騨地方では閉じません。
お寺さんが到着するまでには、準備を済ませておきます。神棚を白い紙で封じる。
神棚がある場合、亡くなられた方を自宅に迎える際に「穢れ(けがれ)」がおよばないようにと、神棚の扉を白い紙で封印します。忌明を迎えたら封じた紙を外します。
ご近所への連絡や枕経の依頼について
- 1ご近所や町内会へのお知らせは?
-
隣近所に対しては、早めに知らせると良いでしょう。ただし、枕経の準備やお寺さんの対応があるので、「亡くなったことの報告・日頃のお礼・車の出入りなどで迷惑をかけるお詫び・詳しいことは改めてお知らせすること」その程度をお伝えすれば良いです。
それ以外には、日時が決まってから、専用の用紙を地域の代表の人に渡して回覧してもらうことでお知らせをするのが、一般的です。
また、お知らせが届くことが、「弔問に行っても良い」という合図でもあります。最近は、ご近所には知らせず身内だけで行う家族葬が増えています。
お知らせを急ぎ過ぎてしまうと、本来、参る人を計画的に制限しなくてはいけないのに、それが出来なくなってしまうので注意が必要です。
- 2枕経(まくらきょう・まくらぎょう)を依頼する
-
手次寺・菩提寺に枕経をお願いします。
電話で依頼するのが一般的です。緊急を要する場合でも、深夜はお寺さんも就寝している可能性があるため、注意が必要です。24時間いつでも受け付けてくださるお寺さんもいらっしゃるので、事前に確認しておくと安心です。昔は送迎をしていたようですが、今はご自身の車で来てくださるのが一般的です。駐車スペースを準備しておきましょう。
お寺に当てが無い場合は、ご相談ください。ご事情にあわせてご紹介します。
- 3枕経の時に行なわれること
-
枕経が済んだ後、葬儀日時の相談を行います。
こちら側の希望と、お寺さん側の都合と、式場の空き状況と、火葬場の空き状況をすり合わせながら葬儀日時が決まります。あらかじめこちら側の希望を、家族や親戚と相談して考えておくとよいです。
他にも、打合せで決めることがいくつかあります。いずれも三礼スタッフが内容を整理して、アドバイスさせていただきます。
- 葬儀に呼びたい他のお寺さんや、読経してもらうお寺さんの人数の希望を伝えます。
- 法名・戒名について、お寺さんからいろいろと尋ねられることもあります。
最初に確認しておいた、生前に授かっている法名・戒名について。手次寺や菩提寺で授かることもあれば、そのお寺の本山(宗派を統轄する寺)から授かることもあります。
正式な手順を踏んでいれば、法名や戒名が書かれたものは、仏壇の引き出しが一般的な保管場所です。
枕元に出しておきましょう。
これらは御布施の金額にも影響するので、経験豊富なご親戚を交えて先に相談しておくとよいでしょう。
- 4枕経が済んだら?
-
お寺さんを交えて、葬儀の日時・お寺さんの人数などを打合せして決めます。
葬儀日時の見通しが立ったら、スタッフが火葬時間の確認と予約をその場で行います。
打合せが済むと、お寺さんは帰られます。一般的に、次にお寺さんに会うのは通夜の式場です。
ただし、通夜までに日がある場合は、身内だけの通夜が行われることがあります。
この場合の服装は、控えめな色味の平服が良いです。礼服では参らないものです。町内会にお知らせをする
お供えの花が届いたりお坊さんが来たり、慌ただしい雰囲気に、ご近所の人たちもなにごとかと心配していらっしゃるはずです。
昔は、ご近所さんに葬式の運営を手伝ってもらっていたので、ご近所さんも相談の場に加わって葬儀日時を決めていました。近ごろは、手伝ってもらうことも無くなったので、葬儀日時が決まってから知らせれば良いです。町内会や班や組の代表の人には、伝え間違いが起きないように、専用の用紙を渡してお知らせをし、回覧をしてもらうのが一般的です。
代表の方が誰か分からない場合・留守の場合は、ご近所の方にどうしたらいいか教えてもらいましょう。弔問の対応
お知らせをしてしばらくすると、回覧を見た人が弔問に訪ねて来るかもしれません。長居なさらないのが一般的なので、お茶を出したりする必要はありません。
参ってくれた親戚への配慮
弔問の応対や葬儀プランの打合せなどを行うため、親戚の人たちの対応に手が回らなくなります。枕経に参ってくれた親戚の人たちには、お礼を述べ、日時を伝え、お引き取りいただきます。
葬儀プランの打合せでは、弁当の個数やご親戚からの供花の取りまとめが欠かせません。家族や親戚代表に配役して、帰られる前に直接聞いて確認が出来ると手間が省けます。
職場や関係先への連絡
電話やFAXやSNSを使って、落ち着いて正確に連絡します。
葬儀の知識
- STEP2葬儀プランの打合せ
-

葬儀はさまざまなサービスや物品が組み合わさったものなので、一つひとつの選択で予算が決まります。
たとえば、火葬場に行く人数が少なかったら、自家用車に乗り合わせることでバスのチャーターをしないで済ませることが出来るのです。カタログをご覧いただきながら、整理しながら順番に決めていきます。
お弁当の数や供花のご注文は、ご親戚との確認をなさった上で決めていただくので、最初の打合せの場で決めていただく必要はありません。死亡届
死亡届とは、人が死亡したことを役所に届け出るための書類のことです。医師から渡される死亡診断書と一枚になっている場合が多いです。
死亡届が役所で受理されると、火葬許可証(打合せ時にスタッフが火葬の予約を行います)が発行されるとともに、戸籍にも死亡の事実が反映されます。
死亡届・火葬許可証の受け取りは、三礼が代行させていただきます。遺影写真・服装・供花について
- 1遺影写真について
-
遺影写真は、一般的に葬儀の斎壇に飾ります。葬儀の後も、忌明けを迎えるまで後飾り壇に安置します。それ以降は、昔は仏間の長押(なげし/鴨居の上の部分)に飾るのが一般的でしたが、最近は飾らないお宅が多くなりました。
写真は、故人の生前の写真から選びます。大きく鮮明に写っている写真が加工に向いています。亡くなる1~5年前の写真が選ばれることが多いですが、元気な頃の写真を選ぶこともあります。終活の一環として、自分で気に入った写真を選んだり撮ったりする方が増えています。
適当な写真が無かったら、撮影しておきましょう。
- 2服装について
-
服装は地域によって違います。
喪主が洋装を選ぶことが増えていますが、飛騨では今でも、喪主は正装である和装を選ぶことが多いです。男性は紋付羽織袴、女性は黒無地の着物です。三礼のレンタル衣裳をご利用になれば、クリーニングも不要でそのまま返却できるため、手間がかかりません。
着付けもうけたまわります。メイク・ヘアセットはお受けできません。
- 3ご親戚からの供花について
-
専用の注文用紙を使って、ご親戚からの供花を取りまとめてご注文ください。喪主は取りまとめ作業や供花代金の集金まで手が回らないので、信頼できる親戚の方にお任せするのが良いです。
供花の並び順は、地域によって違います。
故人に近い関係の人から順に、斎壇に近い場所から並べるのは他の地域と同じです。
飛騨では、喪主は供花を出さないのが普通です。
喪主の兄弟、故人の兄弟、親族、友人、会社関係者の順に並べます。- 血縁上では同列でも、代がかわっている
- 本家を尊重する
など、順番を考える上で判断できない場合は、親戚の年長者に相談しながら決めると良いです。
- STEP3湯かんと納棺
-
安置場所から式場には、棺にご遺体を納めた状態で移送するのが一般的です。
昔は通夜の日の夕方、式場に移送する直前に遺族・親族が集まって湯かん・納棺するのが一般的でした。
今はご遺体の状態を保全するため、早い段階で納棺をし、その状態で通夜の日の夕方、式場に移送するまで安置しておくことが多いです。ただすべてのお宅で、長さ2m程ある棺が玄関と安置場所の間を移動できるとは限らないので、納棺状態で安置することが難しい場合もあります。三礼スタッフが状況を整理して、ご遺体の状態保全を優先してアドバイスさせていただきます。
三礼の安置室を利用すれば、このような心配は解消されます。ご相談ください。
納棺師について
納棺師は、ご遺体を棺に納める前に清め、着替えさせ、化粧などを施す専門職です。
死後、ご遺体には様々な変化が現れます。それらの変化を最小限に抑え、ご遺族が故人との穏やかな最後の時を過ごせるようサポートしてくれます。亡くなられた直後、看護師さんが施してくれるエンゼルケアだけで充分だとお思いのお客様には、無理に勧めることはしません。
副葬品について
副葬品(ふくそうひん)とは、棺に一緒に入れる品物のことです。
故人の愛用品や、冥福を祈るための品物などを入れます。ただし、燃えにくい物や爆発の危険性がある物、焼け溶けて遺骨に付着するなどの影響を与える可能性のある物は避けるべきです。
スタッフにご相談ください。
斎壇への安置~通夜
- STEP1式場への搬送
-
搬送車で棺を安置場所から式場へ運び、斎壇などに安置します。
通夜開式 3時間前~1時間前
3時間前 お棺を迎えに参ります。
葬儀後、骨壺と遺影写真を安置する中陰後飾り壇を三礼が設置します。2時間30分前 ご遺族式場ご到着 供花の並び順の確認・着替えなどをしていただきます。 2時間前 夕飯を召し上がっていただきます。
お寺さんの接待・食事の配膳はお任せください。きめ細やかにお手伝いいたします。1時間前 並んで参列者の出迎えを始めます。
- STEP2通夜開式
-
香典の受付が始まります。
香典の受付方法は、地域によって違います。飛騨では、「会葬お礼」も兼ねて、「香典の返礼品」をその場で渡します。「会葬御礼品」は渡しません。葬儀社によって返礼品はさまざまです。返礼品は数の予想が難しいので、多く注文し過ぎた場合に返品していただける「アルミパックの煎茶」を、三礼では取り扱っております。
飛騨では、受付時に記帳をしません。飛騨にお住まいの方には香典袋に住所も書き添えて持参することが習慣化しているからです。
通夜式
宗派によって式の進行に多少の違いがありますが、経験豊富なスタッフが司会進行・場内の案内を行いますので、ご安心ください。
先にお寺さんが退場し、次に喪主が前に出て参列者にお礼を述べて、通夜式は閉式です。
通夜式では挨拶を述べない方も多いです。通夜式は、30~40分程で終わります。
- 1香典の集計
-
受付した香典の集計、住所・名前をデータ化して記録する代行パックが好評です。忌明けを迎えると、参列や香典のお礼をハガキで送るのが飛騨のやり方です。ハガキの作成まで含まれるので、とても便利です。
- 2駐車場
-
大勢の参列者が予想される場合、安全にお参りいただけるように駐車場の誘導案内係を配置します。
- STEP3通夜後
-
通夜式後、翌朝まで故人に付き添って過ごす方以外も、しばらくは控室に残って、故人を偲びます。大皿料理・酒類・ジュース類の準備・寝具・朝食の手配はお任せください(有料)。
昔から伝わる「寝ずの番」の習慣は体への負担がかかりますので、交代で充分にお休みください。朝まで長持ちするロウソク・線香を用意しておりますので、ご安心ください。
弔電
式場やご自宅に届いた弔電を整理し、数通選んで司会スタッフにお預けください。葬儀式で紹介させていただきます。
焼香順
葬儀式中に個別に指名して焼香してもらうやり方は、最近は行われなくなりました。
「名前の漏れは無いか・読み方に間違いは無いか・読み上げ順は間違っていないか」など、夜通し悩む必要は無いのです。
葬儀~火葬
- STEP1葬儀開式
-

香典の受付が始まります。
通夜に参列なさった方で、葬儀にも参列なさる方はそのまま式場へ向かわれます。宗派によって式の進行に多少の違いがありますが、経験豊富なスタッフが司会進行・場内の案内を行いますので、ご安心ください。
喪主が前に出て、お寺さんと参列者にお礼を述べて、葬儀式は閉式です。
葬儀式は、40分程で終わります。複数人のお寺さんに読経してもらう葬儀では、閉式直後に、御布施を納める必要があります。
タイミングなどはスタッフが案内を行いますので、ご安心ください。
- STEP2お別れ~出棺
-
棺に花をたむけ、最期のお別れをしていただきます。
花は、式場の斎壇を飾った花や、ご親戚に供えてもらった花を切って手向けるのが一般的です。スタッフが準備します。
火葬場への移動
火葬場へお連れする霊柩車・親族用マイクロバス(有料)の手配はお任せください。
人数が多い場合などで自家用車に乗り合わせて向かわれる場合は、慌てることが無いように、予め「誰が運転する誰の車に誰が乗って向かうか」をお決めください。
- STEP3火葬
-
霊柩車には1人同乗が可能です。喪主が同乗するのが一般的ですが、配偶者などの家族が同乗する場合もあります。相談してお決めください。
火葬許可証・骨壺・遺影写真が必要です。忘れたり紛失したりしないよう、スタッフが霊柩車の運転手に直接預けます。
お寺さんは、ご自身の車で火葬場に向かわれます。都合により、お寺さんが火葬場に同行できないこともあります。
これについては、スタッフが事前に確認します。- 1火葬場
-
火葬場では、火葬場の職員の案内に従います。
- 棺を霊柩車から出して、台車に載せます。火葬場職員と、同行した親戚の男性が中心となって行います。
- お寺さんの読経が始まり、喪主から順に線香をあげます。
- 棺の窓越しに、最後のお別れをします。
- 火葬場職員が火葬炉に棺を納めるところを、皆で見届けます。
- 点火スイッチは、飛騨では喪主が押すのが一般的です。ボタンを押すことが困難な場合は、他の遺族や親族、火葬場職員に代わりに押してもらうことも出来ます。
- 火葬が開始されると、お寺さんは帰られます。
- 火葬場職員から、骨揚げ(収骨)の予定時間について案内があります。火葬にかかる時間は、2時間程度です。
- 高山市西洞町にある高山市営火葬場を利用される場合
待合室がありませんので、一度、葬儀場に戻って過ごします。 - 高山市久々野町にある高山市営久々野火葬場を利用される場合
待合室がありますが、遺族ごとに使える個室ではありません。他の遺族と共用で待合室を使用することになります。
- 2お斎(おとき)
-
ご近所さんに葬式の運営を手伝ってもらっていた頃は、感謝の気持ちを表すために食事をふるまいました。最近は手伝ってもらわないので、葬儀に参ってもらった親戚にのみ食事をふるまうのが一般的です。このふるまいの場が「お斎(おとき)」です。接待はお任せください(有料にて代行)。
ただし地域によっては、手伝ってもらわなくてもご近所さんをふるまう習慣が(次第に縮小していますが)守られています。出費は増えますが、共同体の「お互いさま文化」なのでそれに従います。
最初に、喪主や家族の代表者が感謝を述べます。「献杯」が行われることは、ほとんどありません。喪主の「どうぞお召し上がりください」で始まることが一般的です。
お寺さんは同席しないのが一般的です。
- STEP4骨揚げ(収骨)
-
マイクロバスや自家用車で火葬場へ向い、骨揚げ(収骨)を行います。
飛騨地域の多くでは火葬後の遺骨を、全てではなく一部のみを骨壷に納めます。骨揚げが済むと、火葬場のスタッフから「埋葬許可証」が手渡されます。「火葬許可証」に「火葬執行済の認め印」がされたものです。いずれ行う納骨の際に必要なので、骨壺と一緒に保管しておきしょう。
- 1骨壷について
-
遺骨を納める容器は大小2種類で1セット。1つは、高さ20㎝ほどの素焼き製のものです。
もう1つは、高さ8㎝ほどの厚紙製のものです。大きい方は、一般的に家の墓に納めます。
小さい方は主に、各宗派の本山納骨の時に使いますが、これは誰もがしなくてはならないわけではありません。
本山納骨のメリットは主に、次の3点です。
- 開祖の元で手厚く供養してもらえる
- 本山なので運営面での安心感が高い
- 墓石を建立する必要がない
- 2骨壷に収める時
-
遺骨を骨壷に収める時は、「箸わたし」という作法で行います。ひとりが遺骨を箸で拾い、もうひとりが箸でその遺骨を受け取って骨壷に収めるというやり方です。
三途の川を無事に渡ることが出来るように「橋」となることの語呂合わせ、また、皆で行うことで、「悲しみを分かちあう」という意味があると言われています。
2人で特殊な箸を使って行うので遺骨を落としてしまうことがあります。火葬場のスタッフの指示をあおぎましょう。すぐに対応してくれます。決して罰当たりなことではありませんので、心配ありません。
礼参り~ご遺骨安置
- STEP1礼参り
-
飛騨では骨揚げ(収骨)の後に、骨壺・遺影写真・御布施・お供え花(宗派によっては、位牌・卒塔婆が加わります)を持ってお寺に詣でるのが一般的です。
お骨になって最初のお勤めで、宗派によって呼び方は違いますが俗に「礼参り」と呼ばれます。家族や近親者のみで行う場合、火葬場へ同行された方がそのまま行う場合、やり方は様々です。
初七日
ここで初七日のお勤めも繰り上げて行われることが、最近は多くなりました。遠方に住む人にとって、別日にあらためて初七日法要に参加すると負担が大きくなるためです。お寺によっては推奨していないので、事前に確認しておくと良いです。
お勤めが済んだら御礼を述べて、御布施を納めて礼参りは終了です。
親族も揃っている場合は、その場でお寺さんと今後の法要の日程を決めておくと良いです。
- STEP2ご遺骨安置
-

中陰後飾り壇
礼参りが終わり家に帰ったら、骨壺と遺影写真を中陰後飾り壇に安置します。
年金や公共料金などの手続き
人が亡くなると、さまざまな事務手続きが必要です。市役所の手続きは期限が早いので、できるだけ早く行いましょう。
手続きを一箇所で行なえる予約制の「おくやみ窓口」を利用すると、負担を軽く出来ます。
設問に順番答えると、必要な手続きが簡単に抽出できるスマートフォンのサービスもあります。
- STEP3葬儀後
-
弔問の対応
訃報を遅れて知り、弔問のために訪ねて来る人がいます。事前に連絡をしてくれない人もいるので、日頃から玄関や仏間を掃除して、いつでも迎えられる状態にしておきましょう。
香典をくださったら、香典返しを忘れずに渡しましょう。葬儀の際に使った香典返しと同じものを使うのが一般的です。三礼の香典返しのお茶は返品が可能ですので、少し多めにお手元にお持ちください。
中陰(忌中)
命日から数えて7日ごとに7回(宗派によっては5回)お寺さんが自宅を訪ねられ、法要が行われます。7回目(または5回目)までの期間を「中陰(ちゅういん)」とか「忌中(きちゅう)」呼びます。
1回目が「初七日」で、先述の通り礼参りで繰上げて行われることが多く、実際には2回目からで、日中に家族のみで行われるのが一般的です。中陰の法要は「忌引き休暇扱い」にならないので、その日に家に居る者だけで勤めます。
平日であることも多く、なかなか都合がつかない場合は、お寺さんに相談すると良いでしょう。
無理せず可能な時に故人を偲んで手を合わせるなど、敬意や感謝の気持ちを持ちましょう。満中陰(忌明け)
7回目(または5回目)を迎えることを「満中陰(まんちゅういん)」とか「忌明(きあけ)」と呼び、区切りとして家族・親戚の方に集まってもらい法要を営みます。お勤めの後には食事をふるまう、引き物を持ち帰ってもらうなどして、もてなします。
案内ハガキの作成、引き物の手配・配達をお引き受けいたします。ご相談ください。
集まってもらう方の都合もあるので、主だった親戚やお寺さんと相談して早めに日時を決め、連絡しましょう。集まりにくい平日は避けるのが一般的です。「出席」となれば御仏前を持って来られますし、交通費・宿泊費の負担もかけることになります。そこで、最近は近郊に住む親族のみで営まれることも多くなりました。家族や主な親戚と相談して決めましょう。
- 1満中陰(忌明け)のお礼状
-
いただいた香典の三分の一から半額程度の品物を贈る「半返し」と呼ばれる慣習がありますが、高山市では行いません。満中陰(忌明け)を迎えたら、香典をくださった方にお礼のハガキを送るというのが一般的です。
香典の集計・記録の代行パックをご利用になられた場合は、このお礼のハガキ作成もパックに含まれているので安心です。
代行パックをご利用でなくても、お礼のハガキ作成のみもお受けします。お申し付けください。宛先印刷は、エクセルデータ等をご用意くださればお受けします。
- 2満中陰(忌明け)以降
-
月命日・百か日と続きますが、その日に家に居る者だけで勤めるのが一般的です。
故人が亡くなって満中陰(忌明け)後に初めて迎えるお盆のことを初盆(はつぼん)または新盆(にいぼん)と呼び、通常のお盆よりも手厚く供養し会食をする地域があります。
高山市では普段のお盆と同程度に行います。一周忌・三回忌法要は、満中陰法要と同規模で行われることが一般的です。しかしこちらも、近郊に住む親族のみで営まれることも多くなりました。家族や主な親戚と相談して決めましょう。
埋葬
埋葬に関する法律は昭和23年前に制定されました。埋葬(地中におさめる)という言葉からも分かるように、墓や納骨施設以外の方法が無かった時代の法律です。法律的に問題があるのは、遺骨を遺棄した場合・墓地として指定された場所以外に遺骨を埋めた場合です。自宅の敷地であっても庭などに埋めることは違法行為です。
近年は埋葬方法が多様化しています。墓に遺骨を納める以外に、樹木葬・海洋散骨・里山散骨・手元供養などさまざまな選択肢があります。故人の希望を考慮し、遺族が納得できる方法を選びましょう。
埋葬せずに半永久的に手元供養をしても問題はありません。ただし将来的に、手元供養品を引き継ぐ人がおらず、管理できなくなった時にどうするのかについても決めて周囲と共有するようにしましょう。