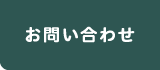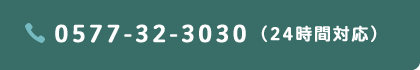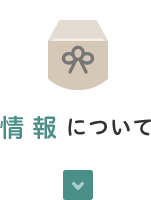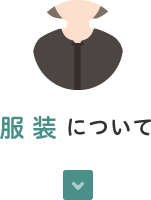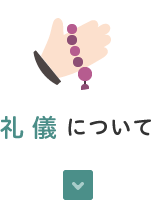葬儀の知識
- HOME |
- 葬儀の知識
葬儀に関する様々な知識を紹介
情報について
家族・近親者への連絡
連絡の基準
| 1親等: 両親・子供 | 最優先で連絡し、すぐに駆けつけられるようにします |
|---|---|
| 2親等: 兄弟姉妹・祖父母 | できるだけ早く知らせます |
| 3親等: 叔父・叔母・甥・姪 | 関係性を考慮して連絡します |
遠方にいる親しい親戚などには、連絡だけはすぐに入れておくと良いでしょう。
- ただし、家族葬をしたいと考えている場合は、連絡するタイミング・範囲・内容に注意が必要です。
家族葬をおこなう式場には収容人数の制限があるのが一般的です。「お参りしてもらう人」と「お参りをお断りする人」を整理して決めなくてはならないからです。
喪主を誰にするか決める
法的なルールはありません。
故人との縁が深い順に、「葬儀費用の負担」「時間的負担」「葬儀を行う上での労力」、「故人の遺言」「候補となる人の年齢や健康状態」などを考慮して、家族で話し合って決めることが大切です。
たとえば
- 夫や妻が亡くなった場合は、故人の配偶者や子供が喪主になります。
- 配偶者が高齢の場合は、子供が喪主になります。
- 故人が若い場合は、親が喪主になります。
- 配偶者がおらず、親が高齢の場合は、兄弟姉妹や甥姪が喪主になります。
- 高齢な母親には肩書だけ「喪主」となってもらい、息子や娘がお寺さんや三礼との交渉や伝達を行うこともできます。
葬儀を行うにあたり、「喪主がやる」とされていることはたくさんありますが、実際は家族や親戚の人たちに助けてもらいながら役割を分担することが可能です。三礼スタッフも、やるべきことを整理してアドバイスやお手伝いします。それほど心配することは無いと思います。
葬儀日時について
時間帯にもよりますが、亡くなった日の翌日を通夜、翌々日を葬儀とする場合が多いようです。
「特定の日に葬儀や火葬を行わない」などの風習を重んじる地域もあります。「友引は縁起が悪い」として葬儀を避けることがありますが、これはあくまで風習で、宗教的な意味はありません。経験豊富なご親戚や、お寺さんを交えて相談するとよいでしょう。
また、ご近所さんに葬式の運営を手伝ってもらっていた頃の名残りで、ご近所さんにも集まってもらって一緒に日時を決めるという習慣を守っている地域もあります。共同体の「お互いさま文化」なのでそれに従います。
遠方からの参列者が多い場合は、移動時間や宿泊なども考慮して日程を調整する必要があります。
三礼が内容を整理して、アドバイスさせていただき、火葬の予約をその場で行います。
ご遺体の安置方法について
ご遺体の安置方法
| 布団安置 | 布団に寝かせた状態で、ドライアイスを使用して安置 |
|---|---|
| 納棺安置 | 棺の中に納めて蓋をした状態で、ドライアイスを使用して安置 |
| 冷蔵庫安置 | 専用冷蔵庫の中で安置 |
布団安置だと、冬場は部屋暖房が使えません。夏場は強冷房で冷やす必要があります。そのためドライアイスを使用しても、長時間安置することは難しいです。
もっとも効果的に冷却できる安置方法は冷蔵庫安置ですが、途中で故人の顔を簡単に見られない点、冷蔵庫が大きく安置場所で使用することが出来ない点がデメリットです。三礼には、冷蔵庫はありません。
したがって様々な面を考慮すると、枕経や弔問が落ち着く頃に納棺してドライアイスで冷却する納棺安置が良いです。
年金や公共料金などの手続き
- 主に必要な手続き
-
- 年金受給停止の手続
- 国民年金の死亡一時金請求
- 介護保険資格喪失届
- 住民票の抹消届
- 世帯主の変更届
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 所得税の確定申告と納税
- 固定資産税の納税・現所有者申告
- 相続税の申告と納税
- 各種公共料金の解約
- 高額医療費の還付申請
- 葬祭費の申請
- 遺族年金の請求
- 故人の未支給年金の請求
- 生命保険金の請求
服装について
故人様の身支度
生前に法名・戒名を授かっている場合、それが記されたものがあるはずです。
仏壇の引き出しが一般的な保管場所です。枕元に出しておきましょう。
生前使っていらした数珠を、葬儀の時に棺に納める習慣があります。飛騨では、故人の手に掛けて持たせるのが一般的です。
ご家族が、「形見として残したい、引き継いで使いたい」とお考えの場合は、それに代わる数珠を掛けてあげます。適当な数珠が無い場合は、棺に納めるための簡易的な数珠を用意しますので、三礼にご相談ください。
輪袈裟(わげさ/細長い袈裟の両端を飾り紐でつなげて輪状にし、首に掛けるもの)があれば、故人に掛けてあげます。
人が亡くなると、日常とは逆のふるまいをおこなう風習が、古くから全国各地にあります。「さかさごと」と呼ばれます。
「死」が「異常である」とか「ケガレである」という考え方や、「故人を守るための魔除けが必要」という考えに基づくものです。
飛騨地方は、宗派を問わず、「さかさごと」があまり行われていません。
枕経の時の服装
控えめな色味の平服が良いです。礼服は相応しくありません。
数珠は、せめて家族は持っていたいものです。もし忘れてしまったとしても心配ありません。
日時などを確認しようとする問い合わせで、携帯電話が鳴ることはよくあることです。場に相応しくない軽快な着信音など鳴らないように気をつけましょう。
礼儀について
お寺さんが到着したら
安置している部屋へ案内し、枕経をあげてもらいます。
30分ほどです。参列する人に決まりはありませんが、一般の弔問客は参加しません。
枕経が済んだら、葬儀日時の相談などが行われます。
お寺さんが着替え終えたら、相談が出来る机のある場所などに案内し、お茶を出しましょう。冷たいお茶でも構いません。茶菓子は付けても付けなくても、どちらでも良いです。一般的にはお茶だけです。
先回り準備をしておきましょう。
枕経の時は、御布施を渡しません。お寺さんによりますが、枕経は葬儀の一連の流れに含まれる儀式と考えられているためです。